こんにちは! 柴野あさぎです。
不登校のケアは、努力が報われなかったり、子どもに振り回される、など精神的に疲れることが多くあります。
この記事では、【親の心が疲れる原因】と【燃え尽き症候群にならないための対策5つ】をまとめました!
疲れの原因は、感情を我慢していたことによる【共感疲労】だという事が分かりました。
 あさぎ
あさぎ不登校の対応はどうしてこんなにしんどいの?という方の参考になったら嬉しいです!
不登校の親はもう疲れたよ…!【私の体験談】
私自身も小学生の兄妹の不登校を1年半体験しています。
不登校からの五月雨登校です。
五月雨登校は【子どものタイミングに合わせて学校に行く】というものです。
できる限りのサポートをしようと思っていましたが、先が見えないのもあり、精神的にしんどい時もありました。
- いつ行くか分からないから、予定が立てられない
- 兄妹バラバラの送迎が疲れる
何が辛い、って自分の主体性が持てないのが辛いですよね。
大したことないと思っていましたが、他の予定ができないことや、感謝なしで当たり前のようにやらないといけないこと。
この二つも心にじわじわとダメージを与え、疲弊していったのだと思います。



- 自分から感謝の言葉を使っていく。
- 辛い時は気持ちをためこまず、受け止める。(ツイッターでもノートでもなんでもOK)
- 自分の意思も尊重する。
意識してできたらよかったなぁ、と今は思います。
疲れの原因は【共感疲労】だった!
どうして、不登校の親ってこんなに疲れるの?
家にいて、子どもと一緒に過ごしてるだけなのに…!
調べてみると、不登校の親は【共感疲労】になりやすいのだと気付きました。
【共感疲労】とは
他者をケアすることから生じる援助者側の心理的疲弊のことです。
これが蓄積されていくと、心のゆとりがなくなり、本来のその人らしさが失われていきます。
共感疲労は、先生や介護士、看護師など、人のケアやサポートする職業の方が多くなる症状です。
なぜなら人をケアする時には、理不尽な言葉や要求をされることがあるため、自分の感情を抑圧して対応する事が求められるからです。



親の目的が【学校に行く】だと苦しくなる
疲れてしまう原因はもう一つありました。
私の目標が【学校に行く】になっていたことです。
この場合、学校に行けた日はとてもご機嫌ですが、行けない日は「えっ、なんで行けないの…」と落ち込みがすごかったです。



その理由は、【自分の目標(夢)を子どもの行動に委ねていた】ことです。
学校に行くタイミングは、子ども自身が決めるものです。
だから子どもをコントロールして自分の目標を達成させるなんて、無理があることだったのです。
これは長男の不登校が終わってからようやく気付きました。
子ども達が学校に行っても行かなくても、親はやりたい事をやり、自分を幸せにして行く事が大切なんだと、実感しました。
そして学校はあくまで自立するまでの、通過地点でしかありません。
学校に行く【結果】ではなく、どれだけ成長したか【過程】に注目することで、心がやっとラクになりました。
不登校の親は【疲れた…】を通り越すと燃え尽き症候群になる!
不登校の子どものケアは、共感疲労を伴います。
「私が我慢すればなんとかなる」と、そのまま対応していると、じわじわと精神的ダメージがたまり、
燃え尽き症候群(バーン・アウト)になってしまう場合もあります。
【燃え尽き症候群】とは
それまでモチベーションを高く保っていた人が、突然やる気を失ってしまう症状です。
努力に見合った結果が出なかった場合や、逆に大きな目標を達成したことで打ち込めるものがなくなり、何もやる気が起きなくなってしまう場合もあります。
医学的には、うつ病の一種とされています。
引用:https://www.kase-cocoro.com/column/burnout.htm
特に不登校期間が長引いている場合や、親子関係が上手くいっていない時は、燃え尽き症候群になる可能性が高いと思います。
燃え尽き症候群になると、感情がなくなる、やる気がなくなる、思いやりをもてなくなる、などの症状が見られます。



疲れた…!燃え尽き症候群にならないための対策方法5つ!
共感疲労が進み、燃え尽き症候群になると、休んでいるのに疲労が全然取れないと感じます。
燃え尽き症候群はすぐには治らないため、日頃からのストレスケアが大切です。
ここでは心が疲れないための対策方法5つをご紹介します。
自分の感情を認める【自己受容する】
ケアが辛い、子どもの暴言が辛い、「でも私が我慢してがんばらなきゃ」では共感疲労が増してしまいます。
だから、自分でその気持ちを受け止めると、少し心がラクになりますよ。
自分で受け止めるのが難しい人は、相談できる人に今の感情を吐き出してみてください。
「私は辛いんだ~。辛いよ~…。もう休もう。」
「どうしてこんなに苦しいの?私ががんばっているから、子どもにも頑張って欲しいのだろうか…」
自分の感情を受け止めることで、感情が落ち着くので、モヤモヤがなくなるのです。
思考がスッキリするので、新しい側面に気付くことができます。
自分の時間を大切にする
ONとOFFのメリハリはしっかりつけた方が、脳も身体もしっかり休まります。
子どもが不登校でずっと家にいると、知らず知らず親も気を使ってしまうんですよね。
だから子どもに遠慮せず、自分が好きなことをする時間を大切にしてください。
カフェで読書、資格の勉強をする、推しのライブに行く、などエネルギーを補充してくださいね。



マインドフルネスをする
不登校の子どもがいると、将来の不安や子どもの行動などが気になり、自分に集中することが難しくなります。
だからこそ、マインドフルネス【今ここに集中すること】がとても大切なんです。
マインドフルネスを続けるだけで、イライラが減り、心が穏やかになりますよ。
私の場合は、上手く物事が進まない時、子どもの言動にイラっとした時に、マインドフルネスを行います。



身近な人に悩みを聞いてもらう
「なんだかモヤモヤするな」と感じたら、誰かに話を聞いてもらってください。
不登校が解決する訳じゃないから、話しても意味がないと思う方がいるもしれません。
しかし、辛い気持ちを吐き出せば、自分の感情を抑圧せずに済みます。



話し相手は、アドバイスせず、しっかり最後まで聴いてくれる人がおススメです。
プロに相談する
自分の気持ちを我慢していると、子どもにも上手く接することができません。
- 子どもの将来が心配で落ち込んでしまう
- 思春期の子どもとコミュニケーションが上手く取れない
- 夫婦仲が悪く、不登校でも疲れ切っていて、笑顔で接する余裕などない
こんな場合は、まずはママの心を癒すのが先です。
幼少期からの思い込みがあると、それに縛られて、新しい思考やチャレンジを受け入れることができません。
過去に抑圧した感情を昇華することができれば、今を受け止めることができますよ。
私の公式LINEでも【LINE電話相談】をしていますので、ぜひご利用くださいね。
【まとめ】心がボロボロになる前に、自分に思いやりを向けよう
不登校のケアやサポートは、自分の感情を抑えて子どもに対応している訳で、知らずのうちに心が消耗しています。



【共感疲労】を防ぐためには、意識して自分の感情を受容することが大切です。
- 辛いもんは辛い!
- 私はこんなにがんばってる!よくやった!
- 今日はカフェでご褒美!わ~‼嬉しい。
嬉しい、悲しい、虚しいなど、我慢せずに、自分で感じる時間を取ってみてくださいね。
燃え尽き症候群にならないためには、自分のやりたい事をやる時間も大切です。
やはり自分が幸せでなければ、相手を幸せにすることはできません。
もう疲れてしまった…。という方は、子どものケアは一旦お休み、自分の回復に専念してみてくださいね。
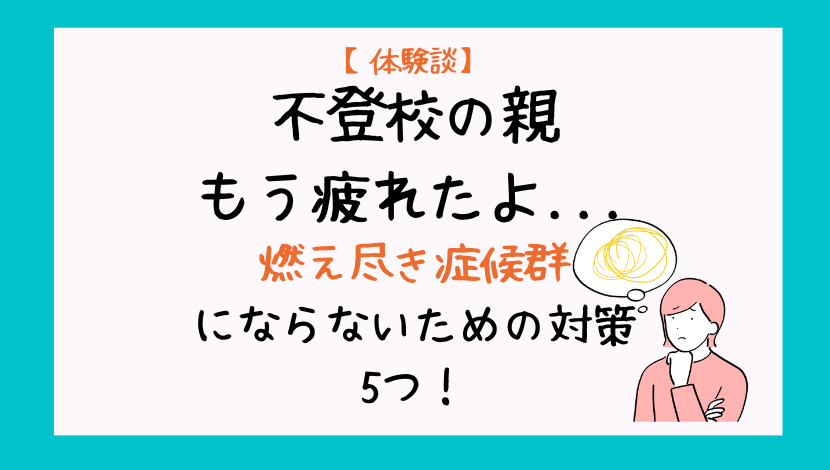
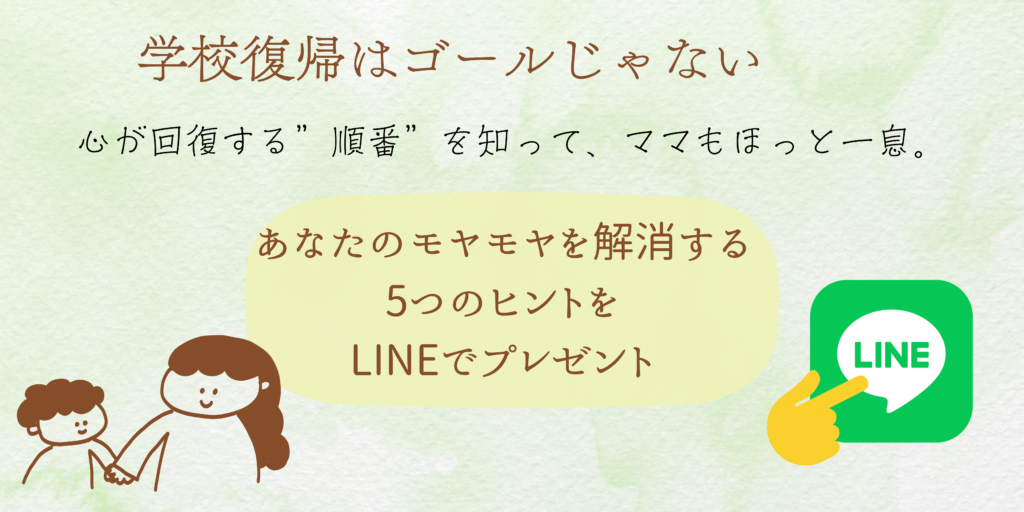
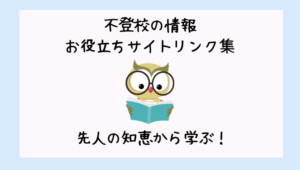
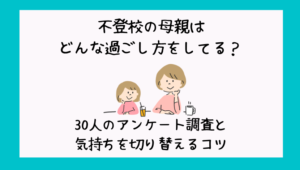
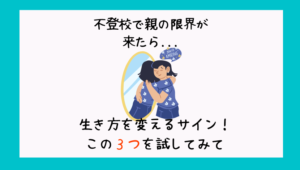
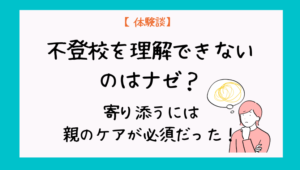
コメント